『フラニーとズーイ』
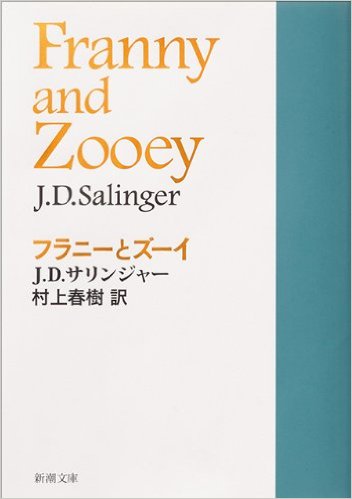
村上春樹訳。
フラニー編がすごい好きだ。
世の中の、自分の回りの何もかもがクソばっかに思えて、気に入らないときってのは確かにある。
それは、彼氏や恋人であっても、当然その例外じゃない(何なら、恋人なんて分かり合えない存在の最たるモンだ)
ここのところわたしは頭がちょっぴりおかしくなっています。
「ああ、あなたに会えて嬉しい!」、タクシーが動き出したときにフラニーはそう言った。「会えなくてすっごく淋しかった」。その言葉を口にしたとたん、それがぜんぜん本心でないことがわかった。そしてこれも罪悪感からレーンの手を握り、指を温かくぴったり彼の指に絡めた。
それを目ざとく感知してしまったことに、罪の意識を覚えなくてはとフラニーは心を決めた。そしてその結果、それに続くレーンの長話を熱心に傾聴する(ふりをする)という罰を、自らに宣告した。
レーンの表情から、自分が場にそぐわない質問をしたことを彼女は悟った。更に具合の悪いことに、彼女は突然もうオリーブなんて食べたくなくなってしまった。どうしてそもそもそんなものをほしいなんて口にしたのか、自分でもよくわからない。
レーンは苛立ちを募らせながら、しばらく彼女の様子をうかがっていた。真剣にデートしている娘が注意散漫なそぶりを見せると、憤慨したり不安を感じたりするタイプの男であるらしい。
「知ったかぶりの連中や、うぬぼれの強いちっぽけなこきおろし屋に私はうんざりしていて、ほんとに悲鳴を上げる寸前なの」。
〜〜よくわからないけど。私が言いたいのは、何もかもがどうしようもなくくだらないってこと」
「この話はもうよしましょう」と彼女はほとんどどうでもよさそうに言った。そして吸い殻を灰皿に押しつけた。
「私はどうかしているのよ。これじゃ、この週末を台無しにしてしまいそう。私の座っている椅子の下に落とし戸があって、このままぱっと消えちゃったらいいかも」
彼はコートから目を逸らし、マティーニ・グラスを見つめた。得体の知れない不当なはかりごとに遭った人のように、憂慮の色を顔に浮かべて。
ひとつだけはっきりしていることがある。この週末はあまり面白くない始まり方をしてしまったということだ。
歯がおかしな感じになるの。がたがた震えちゃうの。一昨日なんて、グラスを噛んで割ってしまいそうになった。私は頭が完全にいかれちゃっていて、それに気づかないだけなのかしら」。
ズーイの章
夢も希望もない講座を抱えていたりはしなかったかもな、と自らに問うこともないではない。でもそんなのはたぶん世迷い言だ。職業的耽美主義者に足して、カードはあらかじめ不利に仕組まれているのだ(感心するくらいに実にぴったりと)。
シーモアがかつて僕にーよりによってマンハッタンを横断するバスの中だぜーこう言ったことがある。
すべてのまっとうな宗教的探求は差異を、目くらましのもたらす差異を忘却することへと通じていなくてはならないんだと。それはたとえば少年と少女の差異であり、動物と石との差異であり、昼と夜との差異であり、熱さと冷たさの差異だ。そのことが唐突に肉売り場のカウンターで僕の心をはしっと打ったんだ。
才知こそが僕の永遠の宿業、僕の木製の義足なのであり、それを人前でわざわざ指摘するのは、決して好ましい趣味とはいえないと言った。
「あんたは結局、言いたいことをぜんぶ言うじゃないか。僕がどう返事をしたところでー」
「僕はある夜、フラニーが外出の支度をしているあいだにそいつと二十分にわたって話をした。底なしに消耗な二十分だ。言わせてもらえば、あいつは巨大な空っぽだよ」
最初の二分間で誰かのことが気に入らなかったら、おまえはその相手を永遠に受けつけない」
「そんなに好き嫌いが激しいまま、この世界で生きていくことはできないよ」
「いずれにせよおまえの妹は、彼はすく頭が切れるって言ってるよ。レーンのことだけどね」
「そりゃ要するにセックスが絡んでいるからさ」とズーイは言った。
僕は誰かと昼食をとって、そこでまともな会話を交わすことすらできないんだ。すごく退屈しちゃうか、それとも偉そうに説教を垂れるかするものだから、少しでもまともな頭を持った相手なら、椅子を掴んで僕をぶん殴りたくなる」
「なんで結婚しないんだい?」
それまでとっていた姿勢を緩めると、ズーイはズボンのポケットから、折り畳まれた麻のハンカチを取り出し、さっと広げた。そして二度か三度、それで洟をかんだ。ハンカチをしまい、言った。「僕は列車に乗って旅行をするのがとても好きなんだ。結婚すると窓際の席に座れなくなってしまう」
「そんなの理由にもならないでしょうが!」
「申し分のない理由だよ。もう出て行ってくれよ、ベッシー。ここで僕に平和なひとときを送らせてくれ。気分転換にエレベーターにでも乗ってきたらどうだい?」